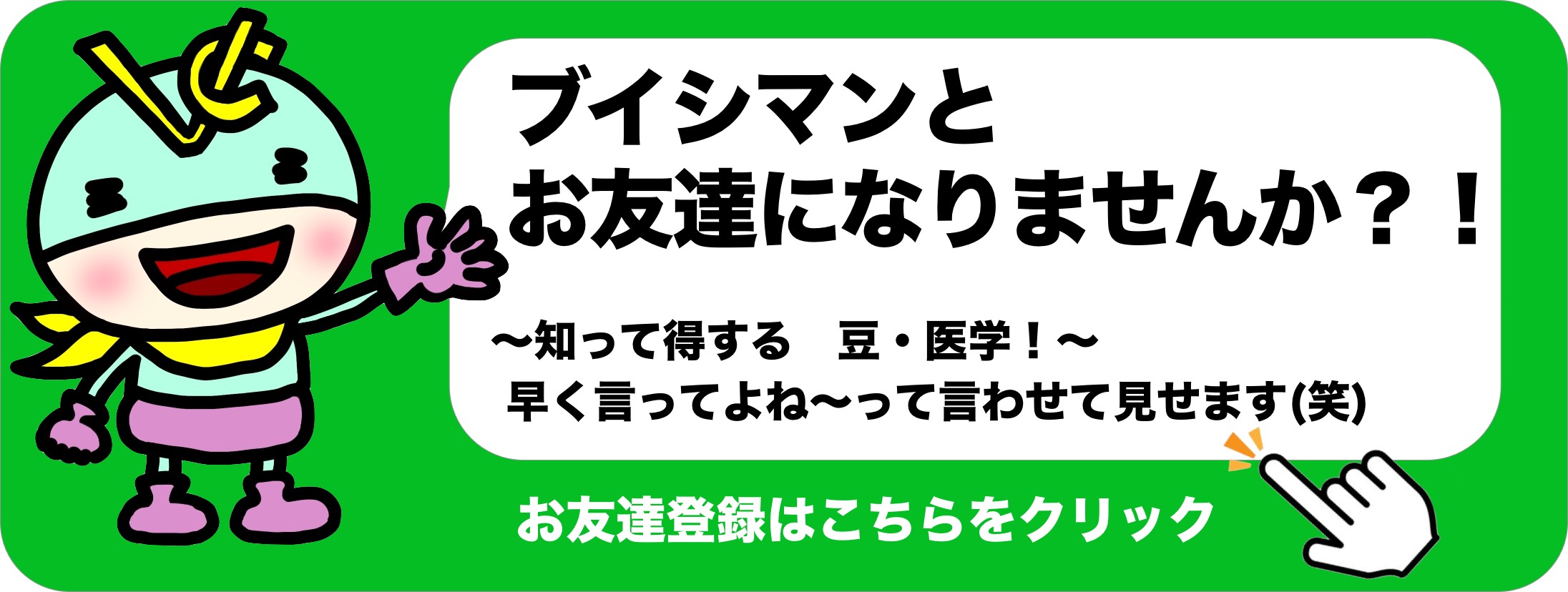どうもこんにちは!ブイシマンです。
ブイシマンが栄養にハマったきっかけは
ビタミンB群のパワーを知ったことなんですが
正直、その当時から
ビタミンB群の名前の付け方って
変じゃない??
って思ってました(笑)

不思議ですよね!
今日は
どうしてビタミンBには
数字がぬけてるのか
そこをスッキリしたいと思います。
とりあえず番号振っとけ!
ビタミンが発見された時
「世紀の大発見!」ということで
世界中が大騒ぎ!!
世界中で
「私もビタミン見つけました!」
という発表が相次いだそうです

ということで
とりあえず仮で番号振っておこう!
というのが「ビタミンB(数字)」
という呼び方の始まりです。
ビタミンの厳しい基準に満たないため剥奪されました
ビタミンと名乗るためには
ちょっとの量でも
物凄く体に大事なのに
自分では作り出せなくて
エネルギーになれないもの
という
結構厳しい基準が存在します。

当初とりあえず数字振っといた
ビタミン(仮)たちは
後になってから
先ほどの基準にはまらないとして
ビタミンから格下げされてしまいました。
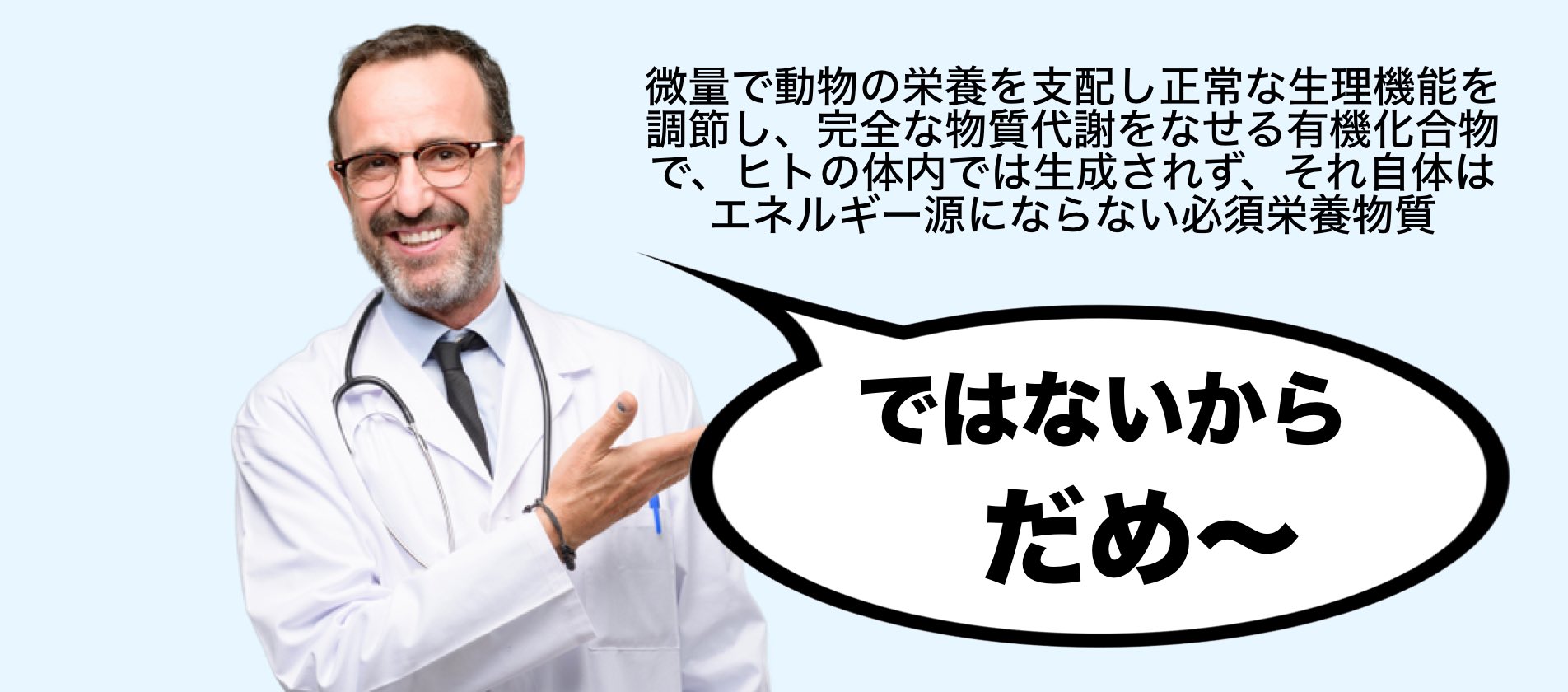
そのためビタミンB群は
歯抜けの数字のビタミンになったのです。
ビタミン競争にエントリーしたB群たち

「はーい!ビタミン発見しました!」
と発表したのち
詳しい精査を経て
無事にビタミンB群になれたのは
たった8個です。
さてあなたには
どれが今も生き残っているビタミンB群か
わかるでしょうか!?
(タップすると詳細が見えます)

化学名・チアミン(ビタミンB群です)
最初に見つかったビタミンであり、かつビタミンの名付け親になった存在です。

化学名・リボフラビン
B2も有名なビタミンB群のひとつですね。

化学名・ナイアシン(ビタミンB群です!)
ビタミンB群は2のあとは6だと思っている方が多いですが、こちらはビタミンB群のひとつとして正式に登録されています。

化学名・アルギニンまたはシスチン(ビタミン様物質です)
残念ながらビタミンの称号は剥奪されてしまいました。

化学名・パントテン酸(ビタミンB群です!)
なんとビタミンB5も存在するんです!

化学名・ピリドキサール(ビタミンB群です!)
こちらは有名なビタミンB群ですね。

化学名・ビオチン(ビタミンB群です!)
なんとなんと!ビタミンB7なんてものもあるんですよ!
 化学名・アデニル酸(ビタミン様物質です)
化学名・アデニル酸(ビタミン様物質です)
調子よくビタミン認定が続いたのですが、残念ながらビタミンの称号は剥奪されてしまいました。

化学名・葉酸(ビタミンB群です!)
女性の多くがよくご存知の葉酸は実はビタミンB群の一種。赤ちゃんのためだけでなく、人が生きる上でとても大切なものなんですよ。なお葉酸はほうれん草の葉っぱから見つかったため、この名前になったと言われています。

葉酸とビタミンB群の混合物でした(今はビタミン様物質と呼ばれています)
葉酸や他のビタミンB群が混ざっただけのものだったんですね。

葉酸類似化合物(今はビタミン様物質と呼ばれています)
このころ葉酸がブームだったようでビタミンB9から立て続けに葉酸が入ったものをビタミンと発表されています。

化学名・シアノコロバラミン(ビタミンB群です!)
ビタミンB12に他の名前があったことを知っていた方、いらっしゃいますか?

オロト酸(今はビタミン様物質と呼ばれています)

葉酸またはリポ酸の混合物(今はビタミン様物質と呼ばれています)
出ました葉酸!またまた葉酸が入ったものがビタミンB群にエントリーされました!これだけ葉酸が多くの方に発見されてエントリーされるところを見るだけでも、葉酸がいかに大切かがわかりますね!

パンガミン酸(今はビタミン様物質と呼ばれています)
もはや聞いたことのない栄養素です。

アミグダリン(今はビタミン様物質と呼ばれています)
ますます聞いたことのない栄養素です。

アミグダリン(今はビタミン様物質と呼ばれています)
まさかのビタミンB16と同じ物質がエントリーされるとは!!

イノシトール(今はビタミン様物質と呼ばれています)
18がくると見せかけて、ここから急にアルファベットになります。

コリン(今はビタミン様物質と呼ばれています)

カルニチン(今はビタミン様物質と呼ばれています)
ダイエットの強い味方のカルニチンは、一度はビタミンにエントリーされていたんですね!

p-アミノ安息香酸(今はビタミン様物質と呼ばれています)
これを最後にビタミンB群に挑んでくる挑戦者はいなくなりました。